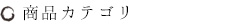信楽焼発症の原点となったきっかけ
信楽は、みず湖では日本最大の琵琶湖南部に位置し京都・奈良の中間で地理的に重要な場所でありました。
その為時の政府が日本の首都にする構想がもちあがり、奈良の盧遮那仏(通称大仏)など行政と宗教の両面を兼ねた壮大なものであったとされています。
そして聖武天皇が天平17年(745年)に、信楽の地に都を造営される為に瓦を焼いたのが、信楽焼発祥の原点です。
それ以来、窯の火は絶えることなく今なお燃えつづけ、やきものの歴史は常に民衆と共にあゆみつづけ、鎌倉時代中期には穴窯により農耕用の水がめ、種壺等の自然灰のかかった素朴なものがつくられました。
茶道の興隆と共に盛り上がる信楽焼
室町・桃山時代になると千の利休による茶道の興隆と共に“わび”“さび”の風合いの茶器の名器がつくられ、後世に珍重されている。
徳川中期以後は、登り窯での焼き方に代わり、茶壷、梅壺、徳利など日常雑器が多くつくられた。
明治以後文明開花と生活スタイルの変化に合わせて「なまこ釉」の火鉢の生産が大部分を占めるようになった。
新たな可能性を広げる信楽焼
昭和35年頃からは植木鉢が主製品となり、以来テーブルセット、建築陶器、置物等を生産し、またEXPO70’では岡本太郎氏の指導のもと「太陽の塔」と共に過去を象徴する「黒い太陽」が制作されたり、昭和50年には、伝統工芸品信楽焼に指定を受け、国会議事堂の外壁にも採用されています。
近年では、西洋名画の作品を特殊技術による陶板画に再現されるなど、内外に信楽焼の名声を高めている。また日常の文化生活を営むデザイン性にすぐれたアイテムも多数焼成され、世界中にひろめられています。