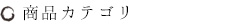
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |

11月は ”茶人のお正月” ともいえる炉開きの季節。
八十八夜につまれた新茶を旧暦の亥の日に祝って飲む行事をいたします。
亥の日は、陰陽五行の中の「水」となり、火に対するものなので
一年の火の用心を祈るためです
風炉から炉に変わる初日を「炉開き」といいます
炉開きには「三べ(さんべ)」
「織部(おりべ)」「伊部(いべ)」「瓢ふくべ」を使うといいと言いますが
これは、密教の曼荼羅(まんだら)で
仏部、蓮華部、金剛部と分かれ三部構成になっている事にちなんでいると言われています
昔の茶人は、今の様な冷却装置(冷蔵庫)がなかったので
1年間常温のまま使っていましたので
今月飲める新茶をとても楽しみにされていたにちがいありません
又、木造家屋での火の元にも大層気を配る。
「炉開き」の伝統を知ると、昔の茶人の思いが伝わってくるようです
お抹茶をいただくのは一緒ですが、風炉で湯を沸かしていたのが、季節が寒くなるので炉を開け,
部屋全体を温め、亭主やお客人にも火が近づくことにも配慮されています
その折、信楽の皆具を使用して手前をするのも、茶人にとってはそれは嬉しいことなのですよ。

